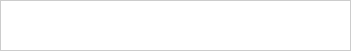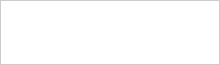(文献紹介)高齢の大腸がん患者に対する術後補助化学療法
(2025年12月15日)
大腸がん(ステージ2または3)手術後の補助化学療法の効果について、7つの臨床試験のデータを統合して年齢別(70歳以上vs70歳未満)で比較した日本の研究が、11月23日にColorectal Disease誌に発表されました。
Hoshino N, et al. Efficacy and safety of oral 5-FU-based adjuvant chemotherapy for geriatric patients with colorectal cancer: Integrated analysis of seven clinical trials conducted at the Japanese Foundation for Multidisciplinary Treatment of Cancer. Colorectal Dis. 2025; 27(11): e70317.
がん集学的治療研究財団メールマガジン第65号(2025年12月15日)
70歳未満の7756人、70歳以上の1706人のデータを統合解析した結果、補助化学療法実施群は手術のみ群に比べて、70歳未満では有意な改善(5年生存率、81.6%対73.6%、p<0.001)が見られましたが、70歳以上では見られませんでした(同、78.9%対76.1%、p=0.129)。ただし、70歳以上であってもリンパ節転移陽性の方では補助化学療法の効果が示されました。
一方で、70歳未満に比べて70歳以上では、補助化学療法の有害事象がより多く見られていました。
高齢患者が増える中で、補助化学療法を行うかどうかを判断する際に患者の“年齢”を考慮することの重要さを示す結果です。
(文献紹介)低価値医療により失われる時間
(2025年12月01日)
不要な医療行為によって医師の貴重な時間が失われることに着目したコラムが、Canadian Family Physician誌11-12月号に掲載されました。
Cheng B, et al. Reclaiming time in family medicine: Unnecessary clinical tasks as a hidden driver of workload burden. Can Fam Physician. 2025 Nov-Dec; 71(11-12): 726-728. doi: 10.46747/cfp.711112726.
本コラムではいくつかのシナリオ(患者の求めに応じて検査を行う例)で、不要な医療に費やされる時間を計算しています。1回当たりの時間はわずかかもしれませんが、積もり積もるとかなりの量になることがわかります。
ムダな医療に費やしている時間を、他のより重要で意味のある医療行為(たとえば患者との対話)に振り向けることで、医師にとっても患者にとっても益になると結んでいます。
(文献紹介)「医療化(Medicalization)」に関するオピニオン3報
(2025年11月17日)
会員の皆様は「医療化(Medicalization)」
という言葉をご存じでしょうか?「
以前は医療の対象とは見なされなかった(中略)
さまざまな現象が、
次第に医療の対象とされるようになっていくこと」(
健康を決める力)を指します。
Choosing Wiselyについて考えていくと、この医療化の問題を避けて通ることはできないんじゃないかと、連絡係は考えております。最近発表された、関連する論稿3本を紹介します。ご参考までに。
(文献紹介)前立腺がん検診に関する欧州RCTの追跡結果
(2025年11月03日)
PSAによる前立腺がん検診の有効性を検討した欧州のランダム化
比較試験(
ERSPC試験)を23年間(中央値)
追跡した結果が、NEJM10月30日号に発表されました。
Roobol MJ, et al. European Study of Prostate Cancer Screening — 23-Year Follow-up. N Engl J Med 2025;393:1669-1680. DOI: 10.1056/NEJMoa2503223
抄録によると追跡の結果、前立腺がん死亡率は、検診群で13%少なく(rate ratio 0.8, 95%CI 0.80-0.95)、リスク減少の絶対値は0.22%(95%CI, 0.10%-0.34%)でした。検診招待者456人(95%CI, 306人-943人)に1人、前立腺がんと診断された12人(95%CI, 8人-26人)に1人が前立腺がん死亡を免れることになるとのことです。
(文献紹介)Choosing Wisely推奨の影響 in スイス
(2025年10月22日)
ビタミンD検査に関するChoosing Wiselyの推奨の影響を、保険データを用いて後ろ向きに分析したスイスの研究が、10月14日にBMC Health Service Research誌に発表されました。
Sallin A, et al. The impact of Choosing WiselyTM recommendations and insurance coverage restrictions on the provision of low-value care: an interrupted time series analysis of vitamin D tests. BMC Health Serv Res. 2025 Oct 14;25(1):1359. doi: 10.1186/s12913-025-13524-9.(オープンアクセス)
スイスのChoosing Wisely(Smarter Medicine)は2021年4月に、特にリスクファクターのない人にルーチンのビタミンD検査(低価値医療とされている)を行わないよう推奨しました。さらに2022年7月には、スイス当局がビタミンD検査に対する保険償還を特定の状況のみに限定しました(それ以外の場合は患者の自己負担)。
保険データを基にビタミンD検査の件数の推移を調べた結果、医師1人の診察100回当たりの検査件数は、推奨が発表されてから1年間で5.98%減少しました。確かに減少はしましたがインパクトとしてはそれほど大きくはありませんでした。
ところが、保険適用が制限されてからの6カ月間では、57.82%と大幅に減少していました。
著者らは、医療従事者向けのエビデンスに基づく指針、患者の関与、保険償還に関する国の規制(保険適用)を組み合わせた多面的な戦略が有効だと指摘していました。
(文献紹介)マイルドな高血圧に対する薬物療法のコクランレビュー
(2025年9月29日)
無治療の”マイルド”な高血圧(収縮期血圧値140~159mmHgまたは拡張期血圧値90~99mmHg、あるいはその両方)で心血管疾患の既往がない成人に対する薬物療法に関するコクランレビュー(改訂版)が、9月24日に発表されました。
Wang D, et al. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2025 Sep 24;9(9):CD006742. doi: 10.1002/14651858.CD006742.pub3.
薬物療法(単剤またはステップアップ療法)とプラセボ(または無治療)を比較した5件のRCT(全9124人、薬物療法群4593人、プラセボ/無治療群4531人)を統合しました。
その結果、薬物療法群はプラセボ/無治療群に比べて、全死因死亡がわずかに少ないが有意ではなく(RR 0.85, 95%CI 0.64-1.14)、総心血管イベント(RR 0.93, 95%CI 0.69-1.24)、冠疾患(RR 1.12, 95%CI 0.80-1.57)も同様でした。
また、脳卒中は減少する可能性がありますが(RR 0.41, 95%CI 0.20-0.84)、副作用による脱落(withdrawal due to adverse effects;WDAEs)はかえって増加する可能性(RR 4.80, 95% CI 4.14ー5.57)がありました。
なお、上記メタアナリシスの結果はすべてlow-certainty evidenceと判定されています。
(文献紹介)COVID-19診断前後の抗菌薬使用と耐性菌
(2025年9月26日)
高齢の外来患者を対象に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診断前後の抗菌薬投与と、その後の耐性菌の同定との関連を検討したカナダ・オンタリオ州におけるコホート研究が、9月23日にNEJM Evidence誌に発表されました。
2020年1月から2021年6月まで、66歳以上の外来患者を対象に、COVID-19診断前後の抗菌薬投与と、半年以内の耐性菌の同定との関連を検討しました。全体で5万3533人のうち8228人(15%)に抗菌薬が投与され、1477人(3%)で耐性菌が同定されました。
抗菌薬の投与は耐性菌の同定と有意に関連しており(調整オッズ比1.24(95%CI 1.09-1.41)、グラム陰性菌に限れば調整オッズ比は1.27(95%CI 1.11-1.46)でした。
(文献紹介)傷洗浄は生理食塩水?水道水?
(2025年9月8日)
傷口の洗浄(wound irrigation)に水道水を使うと生理食塩水に比べて感染が増えるかを検討したシステマティック・レビューが、9月1日にWorld Journal of Surgery誌に発表されました。
Shih PR, et al. Choosing Wisely: Evidence-Based Support for the Efficacy and Safety of Tap Water Versus Normal Saline for Wound Cleansing. World J Surg. 2025 Sep 1. doi: 10.1002/wjs.70079. Online ahead of print.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wjs.700792025年7月以前に発表された臨床試験論文、計12報を統合した結果、傷口の感染には両群間に有意差がみられませんでした(リスク比0.78, 95%CI 0.59-1.03)。一方で、この結果に接した臨床医に対する調査では、多くは傷口の洗浄に水道水を使うことに消極的という結果でした。著者らは、(水道水を用いた)洗浄を広めるには、ガイドラインやオピニオンリーダーからの支援、ソーシャルメディアによるプロモーションが推奨されると述べていました。
(研究紹介)高額医療機器の過剰導入がもたらす影響
(2025年9月6日)
医療経済学会の学術集会で、過剰医療に関する演題が発表されていたのでご報告します。
演題番号C-2 大阪経済大学経済学部 川村結愛さんのご発表です。
28ページになります。
抄録は一般公開されています こちらのURL
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/
もしくは、こちらのURL
(文献紹介)過剰診断会議(9/3-5、於:英国)抄録集
(2025年9月4日)
英国で現在(9月3~5日)開催中の「Preventing Overdiagnosis」会議の抄録集が
BMJ Evidence-Based Medicine誌の付録として公開されています。
全部で119題発表されており、タイトル部分をクリックすると抄録が読めます。
日本からは、帝京大学(元国立がん研究センター)の濱島ちさと先生の演題がありました。
「Evidence-based Healthcare」の著者であり近年では一般向け書籍「Sod Seventy!」がヒットした
ミュア・グレイ先生の演題もありました。過剰診断や過剰治療に対抗するためには
「stewardship」のカルチャーが必要だと述べておられます。
他にも興味深い演題がいろいろ出ています。
(文献紹介)ノルウェーのGPでのChoosing Wiselyの認知度
(2025年8月4日)
ノルウェーのGPを対象に2021年に実施したChoosing Wiselyの認知度調査(オンラインアンケート)の結果が、BMC Primary Care誌に8月2日に発表されました。
Breivoid J, et al. Perceptions of the usefulness of Choosing Wisely among general practitioners in Norway: a nationwide survey. BMC Prim Care. 2025; 26(1): 240. doi: 10.1186/s12875-025-02928-5.
回答したGPは900人(ノルウェーで診療しているGPの18%に相当)。うち、患者から毎日のように不要だと思われる診察/紹介/治療を求められていると答えたのは378人(42%)に上りました。不要と思われる要求があった場合にそれを実行しないことについて患者との合意に達する程度を尋ねたところ「しばしば(Often)」496人(55%)、「ときどき(Sometimes)」が348人(39%)であった半面、「滅多に/決してない(Rarely/Never)」も35人(4%)いました。
Choosing Wiselyについて知っていたのは733人(81%)に上り、うち173人(24%)が過剰診断/過剰治療を減らすのに「非常に有用(very useful)」、425人(58%)が「ある程度有用(useful to some extent)」と評価していました。
最も多くの人が診療を変更(「大部分(to a large extent)」と「ある程度(to some extent)」の計)した推奨は「特定の適応がなく、結果がその後の方針に影響しそうにない検査は避ける(Avoid taking tests unless there is a specific indication, and the test result will affect the further course of action)」でした。他にもいろいろな結果が紹介されています。
(文献紹介)救急部門における低価値検査の実施状況とその影響
(2025年7月28日)
基幹病院の救急部門を受診した患者に対する低価値(low-value)検査の実施状況とその影響を検討したオーストラリアの横断調査が、7月21日にEmergency Medicine Australasia誌に発表されました。
Walker H, et al. Could Low-Value Diagnostic Tests be Compounding Access Block? A Single-Site, Cross-Sectional Study. Emerg Med Australas. 2025 Aug; 37(4): e70100. doi: 10.1111/1742-6723.70100. (オープンアクセス)
オーストラリアのある大学病院の救急部門を受診した18歳以上の患者を対象に、2022年4月の20日間に、Choosing Wiselyで「やるべきでない」と推奨されている10種類の検査(マイナーな頭部外傷に対するCT検査等)がどのくらい実施されたかを調べました。さらに、低価値と判定された検査の指示から結果が出るまでの間の時間を「lost bed time」と定義し、どのくらいの時間が失われたかを調べました。
その結果、1871人の患者のうち424人に、10種類の検査(のうち最低1つ)が行われていました。低価値と判定されたのは全体で48.2%(276/572)で、検査室検査の50.6%(246/486)、画像検査の24.4%(21/86)に上りました。低価値の画像検査100件当たり152時間がlost bet timeと判定されました。
低価値検査は経済的にムダなだけでなく、患者の救急部門滞在時間を長引かせ、その結果として他の救急患者が医療にアクセスするのを妨げているのかもしれません。
(文献紹介)多疾患併存(multimorbidity)患者の治療負担感
(2025年7月22日)
多くの疾患を併せ持っている(multimorbidity)患者の
治療(やケア)の負担感を知るために
英国で開発された質問紙である
MTBQ(Multimorbidity Treatment Burden Questionnaire)の
日本語版を作成し、その妥当性、信頼性を検証した研究が、
7月17日にScientific Reports誌に発表されました。
慈恵医大の青木拓也先生らのご研究です。
Aoki, T., Okada, T., Masumoto, S. et al. Development and validation of a Japanese version of the multimorbidity treatment burden questionnaire. Sci Rep 15, 25991 (2025).
https://doi.org/10.1038/s41598-025-11986-9 (オープンアクセス)
日本版質問紙は、論文の
「Electronic supplementary material」の
「Supplementary Material2」をクリックすると見られます。
「たくさんの薬を服用すること」などの10項目についてその「大変さ」を5段階で答えるものです。
このような方法で患者の治療負担感を知ることにより、治療のやりすぎが「見える化」され、Choosing Wiselyにもつながるのではないかと思いました。
(文献紹介)高齢者への抗菌薬フィードバックの”スピルオーバー”効果
(2025年7月07日)
プライマリ・ケア医に対して高齢者への抗菌薬処方に対するフィードバックを送ることの効果を検討したカナダのRCTの二次解析を行ったところ、高齢者だけでなく全年代で抗菌薬の適正使用につながっていたという結果が、JAMA Network Open誌に7月1日に発表されました。
Saqib K, et al. Spillover From an Intervention on Antibiotic Prescribing for Family Physicians: A Post Hoc Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2025 Jul 1;8(7):e2518261. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2025.18261. (オープンアクセス)
介入群(65歳以上の患者への年間抗菌薬処方件数、他医師との比較、適正使用に関するガイダンスなどを郵送でフィードバック)は対照群に対して、どの年齢層(18歳未満、18-64歳、65歳以上)でも抗菌薬処方の頻度が全体で7%減少(ajusted rate tatio, 0.93; 95% CI, 0.93-0.94)し、7日間を超える処方(無駄と思われる処方)も減少(aRR, 0.82; 95% CI, 0.82-0.83)していました。
ちなみに、元のRCTは以下です。メーリングリストを調べたら、昨年6月11日に紹介していました([cw-j:00378] (文献紹介)高齢者への抗菌薬使用を減らすための介入)
Schwartz KL, Shuldiner J, Langford BJ, et al. Mailed feedback to primary care physicians on antibiotic prescribing for patients aged 65 years and older: pragmatic, factorial randomised controlled trial. BMJ. 2024;385:e079329. doi:10.1136/bmj-2024-079329 (オープンアクセス)
(文献紹介)腰痛に関するChoosing Wisely推奨の理学療法士の行動に与える影響
(2025年6月30日)
腰痛に関するChoosing Wiselyの推奨が、理学療法士の行動に与える影響を検討した、オーストラリアのランダム化比較試験の結果が、BMJ Open誌に6月26日に発表されました。
Kharel P, et al. Effectiveness of Choosing Wisely recommendations in reducing physiotherapists’ intentions to refer for imaging and use electrotherapy for low back pain: a randomised controlled experiment. BMJ Open. 2025 Jun 26;15(6):e097202. doi: 10.1136/bmjopen-2024-097202.
腰痛に携わる理学療法士を(1)腰痛に関するChoosing Wiselyの推奨(簡略版)を受け取る、(2)同じ推奨の詳細版を受け取る、(3:対照群)推奨を受け取らない、の3群に分け、画像検査への紹介および電気療法(electrotherapy)の実施度を、3通りの症例シナリオで調べました。その結果、推奨を受け取る群と対照群との間で、画像検査(OR 0.7(95%CI 0.5ー1.0)~0.9(95%CI 0.6-1.4))、電気療法(OR 0.9(95%CI 0.5-1.7)~1.0(95%CI 0.6-1.7))のどちらとも、点推定値は1を下回ったものの統計学的に有意な差は見られませんでした。
著者らは、たとえ全般的にChoosing Wiselyを支持していても、推奨を単に示しただけでは、理学療法士の行動・判断に影響を及ぼすには不十分であることが示唆されるとしています。そのため、行動を変えるには、いろいろな手段(研修、業務フローの調整、意思決定支援ツール、リマインダーとフィードバック)を2つ以上組み合わせて行うことがよいかもしれないと述べていました。
(文献紹介)「Choosing Wisely Internationalの推奨」
(2025年6月09日)
低価値医療を減らすためのChoosing Wisely Internationalの推奨が、6月4日付でBMJ Evidence Based Medicine誌に発表されました。
Levinson W, et al. Top 15 Choosing Wisely international campaign recommendations to reduce low-value care. BMJ Evid Based Med. 2025 Jun 4:bmjebm-2025-113804. doi: 10.1136/bmjebm-2025-113804.
(文献紹介)「プライマリ・ケアにおけるLVCの実態」
(2025年6月09日)
本研究では、プライマリケアにおけるLow Value Care(LVC)の提供実態を明らかにしました。具体的には、風邪に対する抗菌薬処方やコデイン処方、骨粗鬆症への頻回の骨密度検査など、10項目のLVCを対象としています。その結果、年間でプライマリケアを提供する医師の患者の約10人に1人が、少なくとも1回はLVCを受けていることが明らかとなりました。
また、こうしたLVCの大部分は一部の医師によって提供されており、特に年齢が高い、専門医資格を持たない、診療患者数が多いといった特徴をもつ医師において、その傾向が強いことが分かりました。
▼論文(JAMA Health Forum):
▼日本語での解説記事(筑波大学ウェブサイト):
(報道/文献紹介)診断用AIに対する市民の選好度
(2025年5月27日)
診断用AIの普及に際して、薬剤耐性菌問題を考慮して抗菌薬の使用を最小限に抑える「World-AI」と、薬剤耐性菌を気にせず個人のニーズを優先する「Individual-AI」のどちらを好むかについて、日本など計8カ国・地域(日本、米国、英国、スウェーデン、台湾、オーストラリア、ブラジル、ロシア)の計4万1978人の回答を得た長崎大学の調査結果が、4月にScientific Reports誌に掲載されました。今朝の日経新聞に掲載されていました。
「人類より自分の治療優先して」6割、AI診断にジレンマ 長崎大学など
日経電子版2025年5月18日
(閲覧には登録が必要)
(オープンアクセス)
「World-AI」のみと回答した人は2.3-6.6%だったのに対し、「Individual-AI」のみと回答した人は5.8-24.9%と、どの国でも個人のニーズ優先派が多数派でした(いちばん多かったのは両方あっていい派でしたが)。さらに、日本は「Individual-AI」のみと答えた個人のニーズ優先派が他国に比べて多いという結果でした。
著者は、人々は、薬剤耐性菌の問題が重要であることは理解する一方で、個人のニーズや治療選択肢の自由も重視したいというジレンマを抱えているとまとめていました。
(文献紹介)サウジアラビアのChoosing Wisely
(2025年4月14日)
サウジアラビアにおける国家主導のChoosing Wiselyの成果について、East Mediterranean Health Journal誌2025年3月号に発表されました。
Alsagheir A, Hassanein MH, Alshahri RA. A national intervention to reduce harm by combating overuse of medical services in Saudi Arabia.East Mediterr Health J. 2025 Mar 26;31(3):182-190. doi: 10.26719/2025.31.3.182.
サウジアラビアでは、2021年に国レベルの運営委員会ができ、計画的にChoosing Wiselyを普及・実装を進めています。これまでに20ある地域のうち16でChoosing Wiselyプログラムが(少なくとも一部は)実践されており、9学会が推奨を作成しています。たとえば、ある地域の小児病院では、上気道感染症に対する抗菌薬の使用が25%減るなど、目に見える効果をあげていました。
(2025年4月01日)
Shin S, Roberts SB, Sachar Y, et al. Clinical impact of Choosing Wisely Canada hepatology recommendations: an interrupted time-series analysis using data from GEMINI.
BMJ Open Qual. 2025 Mar 23;14(1):e003142. doi: 10.1136/bmjoq-2024-003142.
検討した推奨は以下の2つです。
・肝性脳症の診断または管理目的で血中アンモニア検査をオーダーしない
・肝硬変の患者の低侵襲的処置に際してルーチンに新鮮凍結血漿、ビタミンK、血小板製剤を輸血しない
オンタリオ州の23病院の入院患者のデータを、2015年4月から2022年3月分まで用いて調べたところ、肝性脳症コホート(1万7906例)では、全期間でみるとわずかに減少していました(1週間当たりの入院当たりで0.002 件の減少 (95% CI −0.00413 to −0.000009))。一方、肝硬変コホート(1万1676例)では、推奨後に新鮮凍結血漿の輸血は増え、血小板やビタミンKの輸血に変化は見られませんでした。著者らは輸血が減らなかった原因として、経験に基づく「慣れ」「習慣」が関係しているかもしれないと述べていました。
推奨を発表しただけでは持続可能な行動変容は起こらないかもしれないという結果は、先行研究でも見られています。Choosing Wiselyも、せっかく公表した推奨を、いかに普及させ、診療に実装するかが問われています。
(文献紹介)Choosing Wiselyの推奨をイラストで紹介
(2025年3月27日)
Choosing Wiselyの推奨(無症状の細菌尿に対して抗菌薬を使わない)を、イラストでわかりやすく患者に伝える取り組みが、3月19日にInfection誌に発表されました。
Heenemann K, et al. Creative illustration for choosing-wisely recommendations on asymptomatic bacteriuria of the Network Young Infection Medicine e.V. – jUNITE. Infection. 2025 Mar 19. doi: 10.1007/s15010-024-02434-3. Online ahead of print.
ドイツの感染症学会のコンペで賞を取った作品が紹介されています。一部の例外を除いて抗菌薬治療は必要ないという内容です。
(2025年3月17日)
腰痛に対する画像検査を減らすというChoosing Wiselyの推奨を促進する目的で、患者と協働でリーフレットを開発したというデンマークの研究が、3月6日にPatient Education and Counseling誌にオンライン発表されました。
リーフレットの開発は、1)腰痛に悩む人にとってどんな情報が必要なのかについて先行研究を系統的に調べる、2)腰痛の診療に従事する5人(GP、理学療法士、カイロプラクター、リウマチ専門医、脳神経外科医)の意見を聞く、3)プログラム理論を構築する(対象者、行動、効果的なメカニズム、短期のアウトカム、中期のアウトカム、長期のアウトカム)、4)エンドユーザーである腰痛の人(18人)へのグループインタビューを基に修正を加える--という4段階で行われました。実際にできあがったリーフレット(英語版)も載っています。
(2025年3月10日)
血流感染症(bloodstream infection)に対する抗菌薬治療の期間(7日vs14日)を検討した国際共同オープンラベル非劣性ランダム化比較試験(BALANCE試験)の結果が、NEJM3月13/20日号に発表されました(オンラインでは昨年発表済み)。
BALANCE Investigators. Antibiotic Treatment for 7 versus 14 Days in Patients with Bloodstream Infections.N Engl J Med. 2025;392(11):1065-1078. doi: 10.1056/NEJMoa2404991. Epub 2024 Nov 20.
血流感染症の入院患者(ICUを含む)を、7日間治療群と14日間治療群にランダムに割り付け、抗菌薬治療を行いました。抗菌薬の種類や量、投与経路は担当医に任されました。治療開始90日以内の死亡は、7日間群14.5%(261/1802)、14日間群16.1%(286/1779)、両群間の差は-1.6(95%信頼区間 -4.0 to 0.8)で非劣性マージン(+4%)を下回り、非劣性を達成しました。
治療期間を短縮することで懸念されるクロストリジウム・ディフィシル感染は7日間群1.7%(31/1814)、14日間群2.0%(35/1794)、耐性菌による二次感染は7日間群9.5%(173/1814)、14日間群8.5%(152/1794)で、いずれも両群間に有意差はありませんでした。
著者らは、7日間治療を採用することは高額薬剤や技術を必要とせず、(抗菌薬の)薬剤費を節約でき、菌の耐性獲得の面でも利益をもたらす可能性があると指摘していました。
(2025年3月10日)
理学療法(physical therapy)に関する各国の学会が、Choosing Wiselyの推奨を発表しているかを調べた研究が、3月1日にBrazilian Journal of Physical Therapy誌に発表されました。
Yi LC, Zadro JR, Soares RJ, Meziat-Filho N, Reis F. Mapping the Choosing Wisely campaigns in physical therapy: Are we missing an opportunity to reduce low-value care? Braz J Phys Ther. 2025 Mar 1; 29(3): 101192. doi: 10.1016/j.bjpt.2025.101192. Online ahead of print.
「World Physiotherapy」のウェブサイトに載っている世界の理学療法系の学会、計127学会のうち、7学会(ブラジル、米国、ノルウェー、イタリア、オーストラリア、スペイン、スイス)がChoosing Wiselyの推奨を発表しており、その半数近く(48.4%)が筋骨格系の理学療法に関するものだったとのことです。
(2025年3月03日)
カナダ内科学会(The Canadian Society of Internal Medicine)による、高価値かつ低炭素のケアに役立つChoosing Wiselyの8項目の推奨が、2月27日にJournal of General Internal Medicine誌にオンライン発表されました。
Gaudreau-Simard M, Shetty N, Silverstein WK, Luo OD, Stoynova V. Eight Ways General Internists Can Practice High-Value, Low-Carbon Care: The Canadian Society of Internal Medicine’s Climate Conscious Choosing Wisely Canada Recommendations. J Gen Intern Med. 2025 Feb 27. doi: 10.1007/s11606-025-09441-6. Online ahead of print.
具体的には以下の8項目です(日本語訳はDeepLの助けを借りました)。
(1)経口抗菌薬で安全に治療できる患者に対して静注抗菌薬を処方しない
(2)経口薬が有効で、患者が好み、医師が安全だと感じていれば、ヘパリン/低分子ヘパリンを処方しない。
(3)同等の有効性を持つ環境により優しい代替品が利用可能で、技術が十分あり、患者の好みに配慮していれば、温室効果ガスを大量に消費する定量吸入器を処方しない
(4)予想される予後や余命について話し合い、ケアの目標を探る以前に検査や介入を推奨/指示しない
(5)特に鎮静薬、PPI、吸入薬は、臨床的適応を確認せずに継続しない
(6)入院患者の管理に変更がなさそうなら毎日の血液検査を指示しない
(7)手指衛生で十分なら滅菌されていない使い捨て手袋を使用しない
(8)オンライン診療が臨床的に適切で、患者が希望すれば、対面でのフォローアップ診療の予約をしない
(2025年2月28日)
台湾や韓国では(日本でも)CT検査機器の普及に伴い、CTを用いた肺がん検診が広く行われるようになっていますが、ヘビースモーカーはともかく喫煙歴のない人にまでCTを用いた肺がん検診を行うことは、過剰診断を増やし、その結果として肺切除術を増やしているとする分析論文が、2月6日にBMJに発表されました。
Welch HG, Gao W, Gilder FG, et al. Lung cancer screening in people who have never smoked: lessons from East Asia. BMJ 2025;388:e081674.
https://www.bmj.com/content/388/bmj-2024-081674
確かに、上海、韓国、台湾のデータ(Fig2)によれば、近年、早期の肺がんの罹患が増えている一方で、進行肺がんの罹患は同程度で減ってはいません。
(文献紹介)検査に関するソーシャルメディアの投稿
(2025年2月28日)
医学検査に関するソーシャルメディアへの投稿内容やそのトーンを分析した横断研究の結果が、2月26日にJAMA Network Open誌に発表されました。
Nickel B, Moynihan R, Grundtvig Gram E, et al. Social Media Posts About Medical Tests With Potential for Overdiagnosis. JAMA Netw Open. 2025;8(2):e2461940. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.61940
ソーシャルメディア(InstagramとTikTok)上に投稿された5種類の検査(全身MRI、がん早期発見、抗ミュラー管ホルモン(不妊治療に使われる)、腸内細菌叢、テストステロン)に関する投稿(英語のみ)、計982本を抽出して内容を分析しました。その結果、検査の利益に関しては87.1%(855/982)で言及されていたのに対して、害については14.7%(144/982)にとどまっていました。また、83.8%(823/982)は宣伝調のトーンで、科学的根拠が明示されていたのは6.4%(63/982)だけでした。
著者らはこれらの結果から、ほとんどの投稿は誤解を招き、過剰診断/過剰使用を含む重要な害について言及していないと結論づけています。
(2025年2月20日)
5種類以上の薬を飲んでいる高齢者(65歳以上)に、減処方に対する意向を尋ねた横断研究の結果が、2月10日にJAMA Network Open誌に発表されました。
Vidonscky Lüthold R, Tabea Jungo K, Weir KR, et al. Older Adults’ Attitudes Toward Deprescribing in 14 Countries. JAMA Netw Open. 2025; 8(2): e2457498.
回答は、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、ドイツ、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイスの計1340人です。主な結果は以下です。
「もし医師が可能だと言ってくれたら、いつもの薬のうち1つかそれ以上をやめたい」
やめたい 1088(81%) やめたくない 239
「やめたらどうなるか知るために薬のうちどれか一つをやめてみたい」
やめたい 648(48%) やめたくない 682
「今の薬のリストのうち、やめたい、または量を減らしたい薬がある」
ある 589(44%) ない 726
やめたい薬として多く挙げられたベスト3は、利尿薬(diuretics)、脂質改善薬(lipid-modifying agents)、レニンアンジオテンシン系に働く薬(agents acting on the renin-angiotensin system)でした。
また、自分のかかりつけ医(GP)を高く信頼している患者は、減らしたい薬を挙げることが少ないことも分かりました。論文の著者は、薬の適切な使用には患者-医療者のコミュニケーションが重要だと述べていました。
(2025年2月19日)
スイスのGPを対象に、非特異的な急性腰痛に対する診療方針について、よくある2症例(架空のヴィニエット)の診療方針を問うアンケート調査の結果が、1月24日にスイス・メディカル・ウイークリー誌に発表されました。
Rrachsel M, Tripppolini MA, Jermini-Gianinazzi I, et al. Diagnostics and treatment of acute non-specific low back pain: do physicians follow the guidelines? Swiss Med Wkly. 2025; 155: 3697.
https://smw.ch/index.php/smw/article/view/3697/6146(heml)
https://smw.ch/index.php/smw/article/view/3697/6152(pdf)
回答者のうち、現在の診療ガイドラインを知っているのは61%、スイスのChoosing Wiselyの推奨を知っているのは76%に上りました。にもかかわらず、実際の診療は、これらの推奨とさほど一致していませんでした。
たとえば、診断に関して「MRI検査を行わない」という推奨に沿っていたのは、症例1では60%、症例2では34%、治療に関して「筋弛緩薬を使わない」という推奨に沿っていたのは、症例1では18%、症例2では20%にとどまっていました。
(2025年2月10日)
第12回CWJオンラインレクチャー(2025年2月9日開催)で演者の和足孝之先生が紹介してくださった、日本でかぜに対する不適切処方(potentially inappropriate prescribing)がどのくらい行われているかを調べた横断研究です。
Nakano Y, Watari T, Adachi K, Watanabe K, Otsuki K, Amano Y, et al. (2022) Survey of potentially inappropriate prescriptions for common cold symptoms in Japan: A cross-sectional study. PLoS ONE 17(5): e0265874. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265874
島根県の病院/診療所を受診し、調剤薬局に処方箋を持ち込んだ併存症のない「かぜ」患者136人を対象に、薬剤師2人と医師(処方医とは別)1人が、処方された薬が「不適切」か「適切」かを判定しました。その結果、「不適切」が89%(121人)に上り、「適切」は11%(15人)でした。
不適切な処方薬として最も多かったのは、細菌感染の症状がないのに処方された経口セフェム系抗菌薬と、呼吸器症状がないのに処方されたβ2刺激薬でした。
(2025年2月3日)
イスラエルの診療データを用いて、限局型大腸がんに対する経過観察目的のPETCT(Choosing Wiselyでは行わないよう推奨されている)について調べた後ろ向きコホート研究が、BMJ Oncology誌3巻1号(2024年12月)に掲載されました(発表は2024年8月7日)
Goldstein DA, Tschernichovsky R, Razi T, et al.
Choosing Wisely in oncology: are guidelines effective at preventing unnecessary diagnostics? The example of surveillance positron emission tomography for patients with localised colorectal cancer
BMJ Oncol. 2024; 3(1): e000391. doi: 10.1136/bmjonc-2024-000391.
この研究で使われたClalit Health Services(CHS)はイスラエル最大の医療保険組織で、人口の52%、450万人が加入しています。新型コロナに対するmRNAワクチンの有効性をリアルワールドで示した研究(NEJM2021; 384(15): 1412-23.)でもCHSの診療データが使われていました。
大腸がん患者1799人を対象にPETCTの回数を調べたところ、0回27.2%、1回20.2%、2回14.5%の順で、0回が最も多かったものの、半数以上の患者で1回以上行われており、10回以上行われていた患者も25人いました。1回の実施は許容する(ステージング目的等と解釈)とした場合、ガイドラインに反する実施が69%に上りました。
医療専門職のガイドライン(Choosing Wisely)があったとしても、PETCTがかなり行われていました。Choosing Wiselyを実装し、不要な検査を減らすには、よりプロアクティブな政策的アプローチが必要なのかもしれません。
(2025年1月27日)
カナダのChoosing Wiselyが2019年から実施している「Hospital Designation Program(HDP)」の取り組みを紹介する論文が、1月21日にJournal of Hospital Medicine誌に発表されました。 Datta D, Day D, Soong C. Improving healthcare value: Choosing wisely canada’s hospital designation program J Hosp Med. 2025 Jan 21. doi: 10.1002/jhm.13593. Online ahead of print.
PMID: 39838712
フェーズ1(2019~2022)では、レベル1~3の3段階が設けられ、最高レベルであるレベル3では、Choosing Wiselyを病院の戦略プランの一部にすることなどが含まれます。一定の成果があったため2022年からはフェーズ2となり「質向上(quality improvement)」と「リーダーシップ」の2分類となりました。 経済的インセンティブや国からの押し付けではなく、根拠に基づくガイドラインの実装をめざす医療専門職の自発的な活動であることが特徴です。